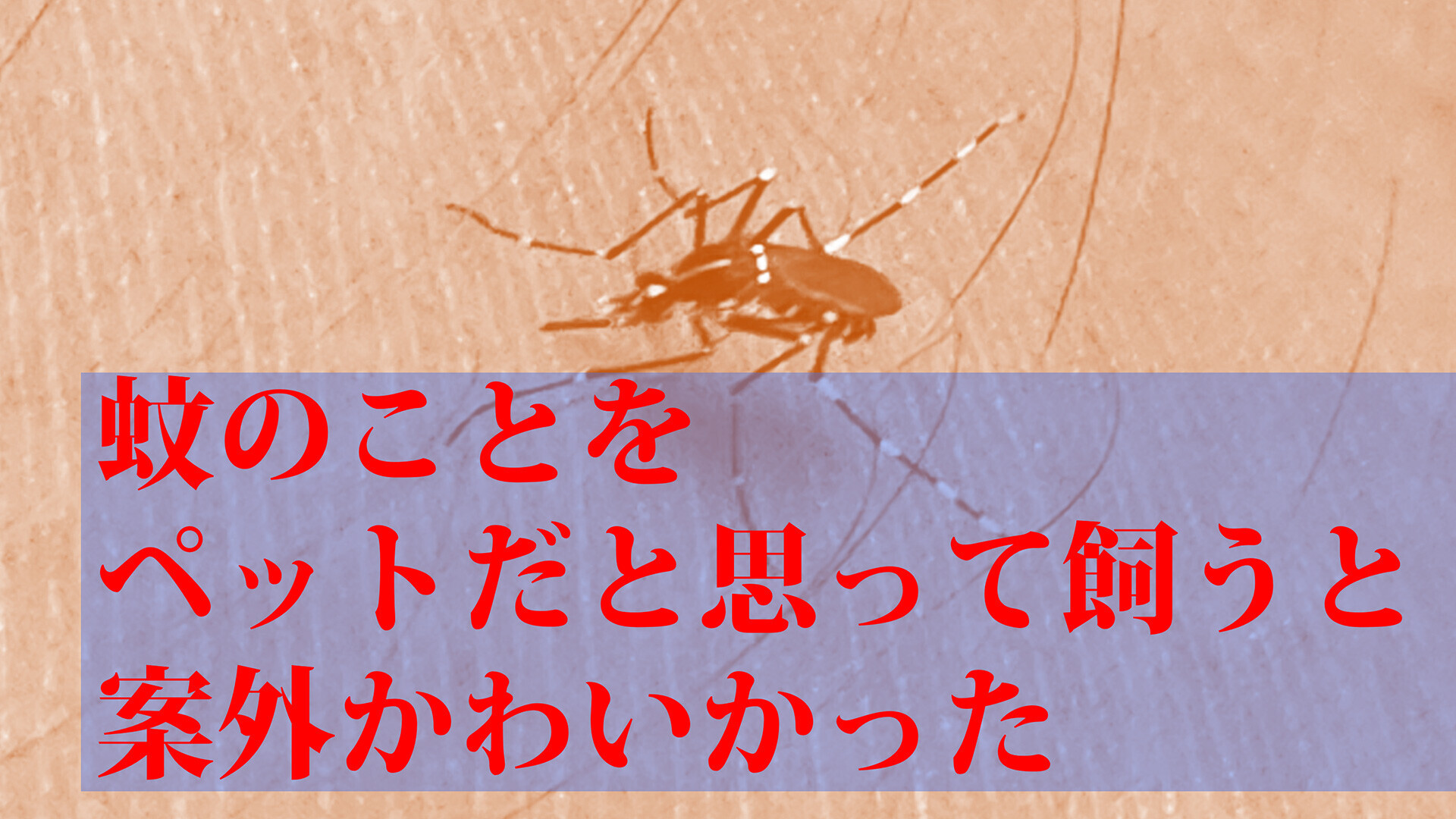
2ヶ月くらい前に玄関で蚊が飛んでいるのを認知するとともに殺害を試みたが、荷物をおろす前だったので動きが緩慢すぎて失敗した。運のよいやつだ。しばらく経ってからまた出会ったので、まだいたのか、早く帰ってほしいと思ったが、退路を塞いだのはわたしだ。扉までも遠かったこともあって二度目の遭遇では殺害を試みることもなく、手で追い払うにとどめた。
よく考えてみると、換気するときでも網戸は閉めたままなので、侵入したとしたら、わたしが家を出るときか家に入ったわずかなタイミングに家に入ってきたということになる。我が家にぜひ入りたいと思って待ち伏せしてくれた蚊なのかもしれない。人間に待ち伏せされたときの、なんでそこにいるの&これから何が起こるのという驚きと絶望はなかなかのものだが、蚊だとその害は多少のかゆみ程度であって、種を超えて向けられた熱烈な好意にわたしは少し感動した。数日後に腕にかゆみを感じたので、それはごはんをじゅうぶんに食べたと理解した。さらに数日経ってもデング熱のような症状はなく、結果として安全だったといえるが、この「結果として安全」という考え方がよろしくないことは不十分ながら認識してはいる。結果として危険だったら、デング熱からデング出血熱にまでステップアップしたのかもしれないから以後気をつけたい。本題とは関係ないが、「デング熱」の「グ」は現地では発音しないのではないかという気がしているが、その「現地」がどこかは知らない。
話を戻して、この蚊の余生は三つ考えられる。
(1)気まぐれな人類によって仕留められて黒い影になる
(2)扉が開くタイミングで外に飛び出してふたたび自由を得る
(3)わたしの家の中で寿命が来るまで過ごす
この時点で(1)はなかった。これだけ想いを巡らせてあの世送りにする選択肢はあるまい。(2)か(3)で、(1)がないなら(2)が普通なのかなと思うが、外に出すのもなんだかさみしい気がしたのと、蚊の感覚からすると、わたしの家にいることを囚われの身であると感じていない可能性がある。蚊の大きさがだいたい5ミリで、わたしの家の長辺が10,000ミリくらい。わたしの身長が1,780ミリだから、わたしが蚊だとしたら、この家の長辺は3.5キロ程度に該当する。自分が何か悪いことをしでかして、半径3.5キロ四方の領域から出てはいけないと言われたら絶望するとは思うが、三食昼寝付きだとしたら……イエスと答えてしまう可能性が高い。旅行などは行けないが、その代わり仕事はしなくてもよいとしたら、かなり魅力的である。そして、その状態に相当する蚊は、わたしの血のみを吸って寿命まで悠々自適の暮らしをおくるのである。
ここまで考えて、わたしは蚊に愛着を持って飼っているといえる状態であることに気づいた。餌はあげなくてよくて、腕に止まったときに排除しなければそれが給餌を兼ねる。トイレはどうしているのかわからないが、わたしが気づかないようなスケールの排泄なのだから好きにしていい。
蚊のことをペットだと思いなしたら、幸せが近くにありすぎてじんわりした。
蚊と暮らすようになってから、蚊のかわいらしさや意外な生態を知ることができたのでここに記しておく。以下の話の一部あるいは全部がわたしの推論の誤りである可能性が高い。しかし、猫を飼っている人が「この世でいちばん偉いのは猫で人間はその下僕」と言ったときに、いちいち「奴隷制度を現代に復活させようというのか!」と憤慨したりしないだろう。それと同じなので、この話も適当に読み流してほしい。
・うちの蚊の吸血成功度は10%にも満たない
蚊のことを、かゆみ注射器や病原菌ばら撒き機だと思っていたときには、刺されてから蚊の存在に気づいて叩いてすりつぶしてあの世に送っていたため、「吸血している蚊のみが蚊である」という偏見を持っていた。いま、家蚊(「家人」のような意味)がわたしの体に止まったら、ごはんの時間が始まったと思って、吸いやすいように筋肉を弛緩させて動かないようにしていたのだが、なかなか血を吸ってくれない。しかも腹が細くなっているのを見ると、今回吸えなかったら餓死するかもしれないと思ってこちらが焦る。家蚊が焦っているかどうかは知らないが、もしのんびりしているのなら緊張感をもって吸血にあたってほしい。
・うちの蚊は吸う限度がわかっていない

これが苦労して血を分けて満腹になった家蚊である。以前、トイレで便座に座っているときに突然お食事タイムが始まったのだが、吸い終わった後、床に落ちて歩いて退却したので心配になった。無限に吸える状況になったとき、飛ぶ余力を残して途中で吸血をやめたりはできないこともあるようだ。食べすぎて吐いてしまう犬などもいるが、蚊だと吸いすぎて仮に吐いたとしても後始末が必要なほどには吐かないので楽なペットである。
・うちの蚊はいなくなって死んだかと思っても明かりをつけたら寄ってくる
帰宅して蚊のいる部屋でしばらく過ごして蚊が飛ばず、ついに召されたかと思うが、Fのつくサイトで半額になっている動画を吟味しているうちに小さな命のことはすっかり忘却の彼方で、そろそろ寝るかと思って部屋の灯りを消して、iPadでジューダスプリーストの動画を見る。すると、どこからともなく蚊がやってきて、画面に体当たりを繰り返す。ジューダスプリーストのファンなのかもしれない。ぼくはそこまでジューダスプリーストのことを好きではないけれど……。
そんな感じでひと夏を蚊と過ごしたのだが、ジューダスプリーストの動画を繰り返し見ても出てこなくなってしまったから召されたのだろう。ペットロスなども皆無だから助かる。
また来年の夏、同じ志を持つ蚊がうちに来たら歓迎しようと思う。わたしの血でよければせいぜい吸ってゆっくりしていってほしい。































































































